[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
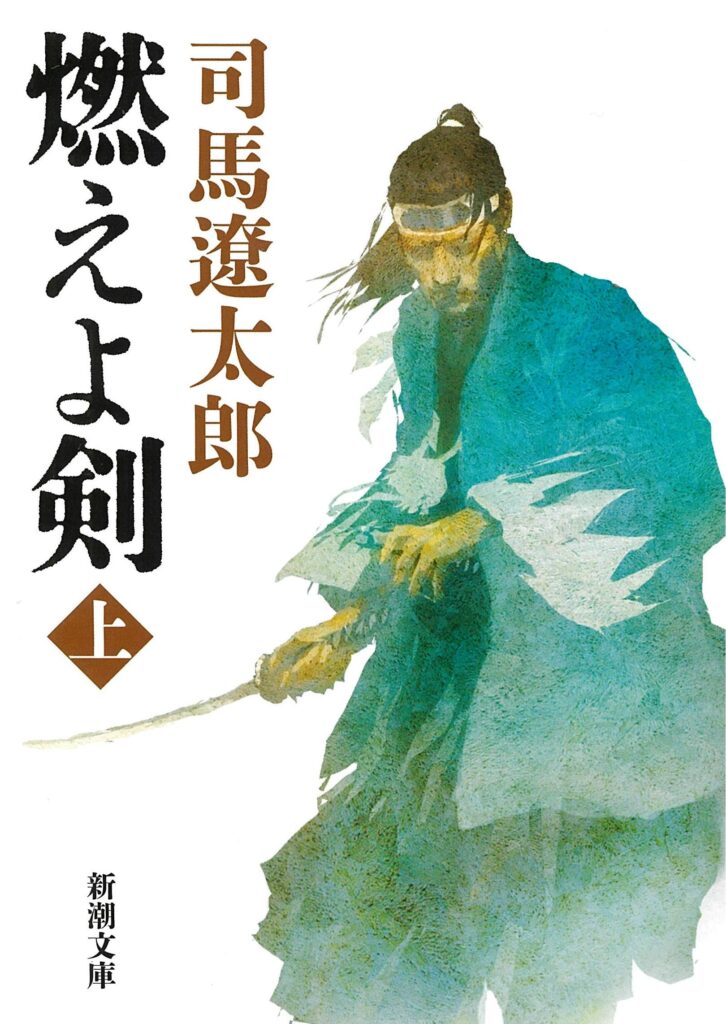
今回の記事では司馬遼太郎のおすすめ小説を紹介します。
・司馬遼太郎の小説を読んだことはないけど興味がある。
・まずどの小説を読むのがいいのかわからない。
・最高傑作はどれ?
という疑問にお答えします。
司馬遼太郎クラスになるとどの小説もおもしろいんですが、作品数もめちゃくちゃに多いので、どれから読めばいいのか悩んでしまいます。
そんなときには今回の記事で紹介した本の中から読んでみて下さい!
司馬遼太郎のおすすめ小説7選
燃えよ剣
佐幕派と倒幕派が対立する幕末の激動期。
武州多摩のバラガキだった土方歳三は、近藤勇、沖田総司らとともに、
幕府徴募の浪士組にまじって、京へ向かう。
京都守護職御預の名のもと、「新選組」を結成。
副長・土方は厳しい局中法度を定め、類のない苛烈な軍事集団を創り上げ、
池田屋事件などで、世にその名を轟かせていく――。
しかし、薩長同盟成立で、時流は一気に倒幕へ。
土方は最後まで激しく抵抗、夢と信念を貫き、江戸、会津、箱館へ向かう。稀代の男の生涯を巧みな物語展開で描いた、傑作長編。
司馬遼太郎の小説を読んだことがない人向けにまずおすすめするのが、燃えよ剣です。傑作であるのももちろんですが、たびたび映像化されている幕末の新選組の話なだけにとっつきやすい人が多いんじゃないかなと思います。
痛快でおもしろく、入門編として読んでほしいです。最高傑作に挙げる人も多く、ここから司馬遼太郎にハマったという話もよく聞きます。
峠
幕末、雪深い越後長岡藩から一人の藩士が江戸に出府した。藩の持て余し者でもあったこの男、河井継之助は、いくつかの塾に学びながら、詩文、洋学など単なる知識を得るための勉学は一切せず、歴史や世界の動きなど、ものごとの原理を知ろうと努めるのであった。さらに、江戸の学問にあきたらなくなった河井は、備中松山の藩財政を立て直した山田方谷のもとへ留学するため旅に出る。
新潮文庫より
個人的には、司馬遼太郎の小説をいくつか読んだ後に読んでほしい作品です。作者が主人公・河井継之助を描くことを楽しんでいる様子が伝わってくるからです。
とにかく河井継之助の人生・未来が気になり、どんどん読み進めてしまいます。眠い目をこすりながらページをめくる手が止まらなくなりました。クライマックスのシーンが美しく、素晴らしい読後感を残してくれる小説です。
項羽と劉邦
紀元前3世紀末、秦の始皇帝は中国史上初の統一帝国を創出し戦国時代に終止符をうった。しかし彼の死後、秦の統制力は弱まり、陳勝・呉広の一揆がおこると、天下は再び大乱の時代に入る。――これは、沛のごろつき上がりの劉邦が、楚の猛将・項羽と天下を争って、百敗しつつもついに楚を破り漢帝国を樹立するまでをとおし、天下を制する“人望”とは何かをきわめつくした物語である。
新潮文庫より
数多くの作品の中でもダントツのスケールを持つ作品です。始皇帝によって中華統一を果たした秦がなぜ滅びるのかというところから物語はスタートします。
項羽と劉邦の対決を描きつつ、国の統治の難しさ、トップに立つことの難しさなど現代に通じるテーマがいくつも示されます。経営者の方、管理職となって部下を指導する立場の方におすすめの作品です。
世に棲む日日
長州萩・松本村の下級武士の子として生まれた吉田松陰は、浦賀に来航した米国軍艦で密航を企て罪人に。生死を越えた透明な境地の中で、自らの尊王攘夷思想を純化させていく。その思想は、彼が開いた私塾・松下村塾に通う一人の男へと引き継がれていく。松陰の思想を電光石火の行動へと昇華させた男の名は、高杉晋作。身分制度を超えた新しい軍隊・奇兵隊を組織。長州藩を狂気じみた、凄まじいまでの尊王攘夷運動に駆り立てていくのだった……
文春文庫より
主人公の高杉晋作の行動力と素晴らしいバランス感覚を持った世渡りがおもしろいです。少しでも選択を誤れば、倒幕という目標は果たせなくなってしまう中、慎重かつ大胆に行動を起こしていく高杉晋作の姿に感心されられます。
他の作品と違うのは、幕末の時代的背景がしっかりと描写されている点です。ほかの作品では主人公や登場人物の描写にページが割かれますが、世に棲む日日では背景や思想が描かれていきます。
国盗り物語
世は戦国の初頭。松波庄九郎は妙覚寺で「知恵第一の法蓮房」と呼ばれたが、発心して還俗した。京の油商奈良屋の莫大な身代を乗っ取り、精力的かつ緻密な踏査によって、美濃ノ国を〈国盗り〉の拠点と定めた!戦国の革命児斎藤道三が、一介の牢人から美濃国守土岐頼芸の腹心として寵遇されるまでの若き日の策謀と活躍を、独自の史観と人間洞察によって描いた壮大な歴史物語。
新潮文庫より
全四巻のうち、前半二巻は斎藤道三、後半の二巻は道三の娘婿となる信長を描いていきます。一介の油売りから一国を支配するまでに成り上がった道三についての描写がテンポ良く読みやすい作品です。
竜馬がゆく
幕末維新史上の奇蹟といわれる坂本竜馬。土佐の郷士の次男坊、しかも浪人の身でありながら、大動乱期に卓抜した仕事をなしえた。 竜馬の劇的な生涯を中心に、同じ時代をひたむきに生きた若者たちを描く、大歴史ロマン。
文春文庫より
幕末の重要人物・坂本龍馬の半生を描いた作品です。史実に基づきつつところどころフィクションを交えて描かれる竜馬の姿がとても魅力的です。完全に史実というわけではありませんが、登場人物の魅力に夢中になると思います。
坂の上の雲
日露戦争を勝利に導いた秋山好古・真之兄弟。俳句改革に命をかけた正岡子規。 伊予松山出身の3人を中心に、明治という時代の明暗と、近代国家誕生にかけた人々の姿を描く、不滅の国民文学。
文春文庫より
司馬遼太郎の作品の中で、入門編を選ぶとするなら『燃えよ剣』ですが、最高傑作を選ぶとするのなら『坂の上の雲』です。
明治の時代を迎え日本が西洋化していく中で、「日本とは?日本人とは?」という問題提起をしている本でもあります。大長編で敷居が高いと感じるかもしれませんが、魅力的な登場人物が織りなすダイナミックなストーリーを楽しんでもらいたいです。
終わりです。ほかにもおすすめの作品を選んでいるので、こちらもどうぞ。
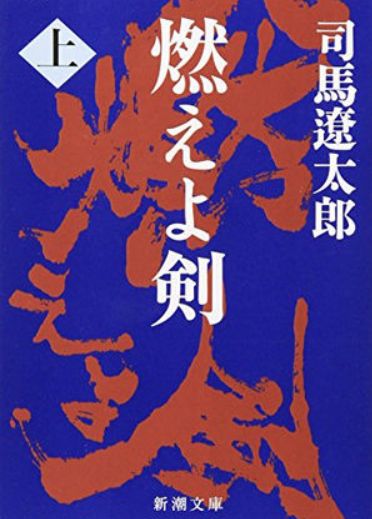







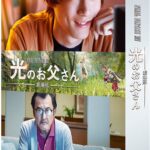

コメント