[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
パイドン(プラトン)の作品情報
- タイトル
- パイドン 魂の不死について
- 著者
- プラトン
- 形式
- 対話篇
- ジャンル
- 哲学
- 執筆国
- 古代ギリシア
- 版元
- 不明
- 執筆年
- 不明
- 初出
- 不明
- 刊行情報
- 1998年、岩波文庫
- 翻訳者
- 岩田靖夫
パイドン(プラトン)のあらすじ
ソクラテスの死刑当日を舞台とした作品であり、『メノン』に続いて想起説が取り上げられる他、イデア論が初めて登場する重要な哲学書である。
作者
プラトン(紀元前427年 – 紀元前347年)
古代ギリシャを代表する哲学者。アテネの名門の家系に生まれる。師ソクラテスとの出会いとその刑死をきっかけに哲学の道に入り、40歳ころには学園「アカデメイア」を創設して、晩年まで研究・教育活動に従事した。ソクラテスを主人公とする「対話篇」作品を生涯にわたって書き続け、その数は30篇を超える。主な作品として、『ソクラテスの弁明』『プロタゴラス』『メノン』『パイドン』『饗宴』『国家』『法律』などがある。その壮大な体系的哲学は、後世の哲学者たちに多大な影響を及ぼした。
パイドン(プラトン)の刊行情報
- 田中美知太郎、池田美恵訳『ソークラテースの弁明・クリトーン・パイドーン』新潮文庫、改版2005年
- 岩田靖夫訳『パイドン』岩波文庫、1998年
- おすすめ納富信留訳『パイドン 魂について』光文社古典新訳文庫、2019年
パイドン(プラトン)の登場人物
ソクラテス
70歳、最晩年。「国家公認の神々を拝まず、青年を腐敗させる」と告発され、牢獄にて毒をあおり刑死する。
ケベス
テーバイ出身のソクラテスの弟子。非常に鋭い頭脳の持ち主。ソクラテスと議論を交わす。
シミアス
テーバイ出身のソクラテスの弟子。ソクラテスと議論を交わす。
パイドン
エリス出身のソクラテスの弟子、哲学者。ソクラテスの死に立ち会う。本書はソクラテスの最後の一日の様子をエケクラテスに伝えるという形式で始まる。
パイドン(プラトン)の概要
一 序曲
師ソクラテス死刑の日に獄中で弟子達が集まり、死について議論を行う舞台設定で、ソクラテスが死をどのように考えていたか、そして魂の不滅について話し合っている。パイドンとはエリス学派の創設者である哲学者エリスのパイドンを指し、ソクラテス臨終の場に居合わせなかったピュタゴラス学派の哲学者エケクラテスに、その様子を語っているという設定でもある。
なお、著者のプラトン自身は病欠しており、師の最期の姿を見ることは叶わなかった。
二 死に対するソクラテスの態度
弟子たちが朝一番に牢獄に向かうと、刑務委員がソクラテスに本日死刑が執行される旨を通知していた。牢獄に来てからのソクラテスはイソップの物語を詩に作り替えたり、アポロンを称える讃歌を作ったりなど、文芸・創作活動に精を出していた。理由を尋ねられたソクラテスは、「この世を去る準備の一環」として文芸を行うことを勧める夢に従ったことを明かした。
さらにエウエノスには、「もし彼に思慮があるのならできるだけ早く自分の後を追うよう」に伝えてほしいと伝える。仲間のシミアスとケベスがその発言の真意を問い、死について問答が始まる。
・「死」についての問答
人間にとって生きることよりは死ぬことの方がより善いということだけが、他のすべてのこととは違って、例外なしに無条件的であり、他のものごとの場合のように、ある時ある人には、という条件がけっして付かない、ということは。
岩田靖夫訳、岩波文庫より
ソクラテスは「我々は神々の所有物の1つなのだから、その所有物が自分自身を殺せば、神々は腹を立て、処罰を加えようとする」と、人間は神々の所有物であることを示す。しかし、ケベスとシミアスは、思慮ある哲学者が神の元を喜んで去るという主張はおかしいと指摘する。
・魂と肉体の分離・哲学者の生き様
ソクラテスは、本当に哲学を行っている者は、ただひたすらに死ぬこと、死んだ状態にあること以外の何ごとも実践していないと主張。ソクラテスは、哲学者たちは自分たちが死人同然の生き方をしている意味を解っていないと言う。つまりソクラテスは「死とは魂の肉体からの分離」であると伝えるのだ。
哲学者は贅沢からも離れ、思索のみから知恵を獲得する。その際肉体というものは邪魔になるだけで役に立たない。
純粋な思惟それ自体のみを用いて、存在するもののそれぞれについて純粋なそのもの自体のみを追求しようと努力する人である。
岩田靖夫訳、岩波文庫より
正義・美・善や物事の本質、真実在は、純粋な思惟のみで追求されるべきものなのだ。そのためソクラテスは、哲学者は生きている間は知恵を獲得できないし、「魂を肉体からできるだけ切り離し、魂を自分自身として凝集し単独で生きるように習慣づけること=カタルシス(浄化)」の重要性を訴える。
ソクラテスにとって真正の哲学者とは、死ぬ練習をしており、死も恐れない者だと言える。
三 霊魂不滅の証明
ケベスは、「魂は肉体と分離されると、もはやどこにも存在しないのではないか」と考える人もいると指摘。これにより、本書にて最長となる霊魂不滅の証明が始まる。
「死者は生者から生まれ、生者は死者から生まれる」という循環や、想起説による証明が試される。ソクラテスは「美そのもの」「善そのもの」を例に挙げ、生まれる以前に「そのもの」が何であるかという知識をどこかで得ていたからだと指摘する。それらの知識は生まれるときに失ってしまうが、後からそれを再発見するのだ(=想起)と述べる。
ケベスは「生まれる前に魂が存在したこと」だけではなく、「死後にも魂が存在すること」も証明しなくてはならないと主張。だが、ソクラテスはこの想起説による証明と、その前の循環の証明を結びつければ、既に証明されているとする。
ソクラテスは、魂は神的であり、不死であり、自分自身と同一のものであるが、肉体は人間的で可死的であるとする。魂が純粋な姿で肉体を離れたならば、その場合魂は肉体的な要素を引きずっていない。魂は肉体を避け自分自身に集中しており、このことこそが正しく哲学することに他ならない。人間的な悪から解放されて幸福になるのだ。
逆に肉体的な欲望・快楽に囚われた魂は重荷であり、やがて獣の中に入るまで彷徨することになる。
哲学をした者、まったく浄らかになって立ち去る者、学を愛する者にのみ、神々の種族の仲間入りが許される。
・シミアス、ケベスによる反論
これにシミアスは、「魂が肉体の調和ならば、肉体の壊滅と同時に魂も死滅するのではないか」と反論。ケべスは、「魂が肉体より長命だとしても、幾度も肉体を着潰すうちに披露し衰弱して滅びるのではないか」という可能性を指摘する。
議論は終わりが見えず周囲の空気は重くなるが、ソクラテスは言論を嫌うことよりも大きな災いはないのだから「言論嫌い(ミソロギア)」に陥らないよう諭し、二人の説に丁寧に答えていく。そして「魂の不死」に関する最終証明を進めていく。
・「魂の不死」の最終証明
ソクラテスの「身体のうちにに何が生ずると、それは生きたものとなるのだろうか」という質問に、ケベスは「魂が生ずると、です」と回答。
続いてソクラテスが「生に反対のものに何かあるだろうか」と尋ねると、ケベスは「死です」と答えた。するとソクラテスは先の議論から、魂は自分が常にもたらすもの(生)とは反対のもの(死)を決して受け入れないと指摘する。ここに「魂が不死」であることは証明された。
「不死」は「不滅」(「魂は不死であり不滅」)である。魂は本当にハデス(冥界)に存在するという結論が導かれ、疑問を示していたケベスおよびシミアスはソクラテスに同意する。
四 神話―死後の裁きとあの世の物語
最後にソクラテスは死後の話を始める。魂が不死であるならば、未来永劫魂の世話をしなくてはならないし、魂が冥界に持っていけるものは自身の教養と養った性格だけである。自己救済のためには善く賢くなるしか方法はない。
人が死ぬと各人に割り当てられたダイモン(神と人間の中間に位置する超自然的能力を持つ霊)がその魂を裁きの場所へと連れていき、魂は裁きを受けてから冥府へと赴き、死から一千年もの期間を経て再生するという。
死者の魂は、生前の生活や行動によって行き先がわかれており、普通の生を送った者たちは善悪に応じた賞罰を受ける。神殿泥棒や不正な殺人などの大罪を犯した者は、タルタロス(奈落)へ投げ込まれ、決して脱出することができない。
敬虔に生きた者は、地下の場所から解放されて自由になり、上方の清々しい住まいに到達し、真の大地の上に住む。特に哲学によって充分に己を浄めた人々は、肉体から離脱した生を送り、もっと美しい住まいに到着する。
五 終曲―ソクラテスの死
日暮れが迫りいよいよ死の時間が近づくと、ソクラテスは皆が自分たち自身を配慮し、これまでの議論に従って生きてもらうことを希望する。その後ソクラテスは沐浴すると、上機嫌に毒薬を受け取り、神々に祈りを捧げてから、平然とそれを飲み干す。
周囲の者たちが泣いて見守る中、指示通り歩き回るとソクラテスは仰向けに横たわる。下半身から麻痺が広がる中、クリトンに対する「アスクレーピオス(医療の神)に雄鶏一羽を捧げてほしい」という依頼が最期の言葉となった。クリトンが他に言うことはないか聞き返すも返事はなく、しばらくして体がピクリと動いたので顔の覆いを取ると、ソクラテスはすでに絶命していた。
その姿を見たパイドンは、これが知りえたかぎり当代のうちでもっとも優れた、特に知恵と正義においてもっとも卓越した人の最期であったと綴っている。
パイドン(プラトン)の感想・評価
魂の不死について
ソクラテス最期の日を舞台に哲学者の「魂」と「肉体」についてソクラテスの考えが展開されていく。主にソクラテスと対話を行うケベスとシミアスは、ソクラテスの考えに同意せず議論を展開するが、最晩年のソクラテスは見事に2人の疑問を解決して見せる。
ソクラテスが語る、「本当に哲学を行っている者は、ただひたすらに死ぬこと、死んだ状態にあること以外の何ごとも実践していない」「死とは魂の肉体からの分離」という主張はなかなか呑み込めないものかもしれない。ケベスの「魂は肉体と分離されると、もはやどこにも存在しないのではないか」という指摘は誰だって頭に浮かぶものだろう。
これにソクラテスは想起説をも用いて「魂」と「肉体」の関係を解きほぐしていく。「魂は不死であり不滅」であることに2人は同意。中期プラトンの代表作ともいえる『国家』に繋がる著作であり、イデア論が初めて登場するという意味でも重要な位置を占めている。
イデア論の提出
イデア論とは、ソクラテスが懸命に定義しようとした正義、善、美などの永遠不変の実存性として出発した。
この世界の「正義」や「美」はいずれも不正や醜さが入り混じっているが、ともかくそれらには正義のイデアや美のイデアが含まれているのである。
「どう生きるべきか」という問いを持ち続けてきたソクラテスは、善や正義の真実を知りそれを実践する自己を求めてきた。『パイドン』においては魂は「イデアを思惟する永遠不滅の霊魂」へと変身したのだ。
勇気を貰える哲学書
師ソクラテスの最期の一日を題材にソクラテス・そしてプラトンの思考が論じられていく。想起説、イデア論などプラトン哲学の重要な位置を占める作品だ。
それに加え、死を目前にしながらも哲学者の崇高な意思に燃えるソクラテスの姿が印象的な一冊である。ソクラテスの生き方(そして死に方に)不思議と勇気を貰えるだろう。
合わせて読みたい本
パイドン(プラトン)の評判・口コミ・レビュー
#プラトン の「パイドン」#読了
— 右手@読む本辞典 (@migite1924) 2019年8月22日
ソクラテス最期の一日を舞台に、哲学者の魂と肉体の関係について論じた一冊。
「本当に哲学を行っている者は、ただひたすらに死ぬこと、死んだ状態にあること以外の何ごとも実践していない」ってソクラテスの考えは達観してる…のかなぁ🤔https://t.co/VVP4pqYfm4 pic.twitter.com/IFcR52pLag
プラトン『パイドン』読了
— よみしろ (@neffle_x) 2019年9月17日
哲学書にしてはかなり読みやすい。言及されることの多い本で、読んでる期間に他の本で触れられるのを見かけて楽しかった。本書は魂が不死であることをイデア論を下支えにして論じる。納得はできないのだが、どこを切り崩せばいいのか分からないのが厄介。
プラトン『パイドン』読了。これまで、プラトンの著作をいくつか読んできて、どちらかというと話の内容より、議論の成り行きを将棋の対局を見るような気分で読んできたのだけど、この『パイドン』は話の内容への興味が勝った。なかなか刺激的で面白かった。
— 日下春生(zsphere) (@faketaoist) 2014年11月21日
プラトン著『パイドン』読了。哲学者とは死というものに真に向かい合っている人なんだなーソクラテスは魂は不滅であると説く。生まれる前に身に付いたことが、(親に教えられずに)自然と行動していることって確かにあると思う。またこの対話は納得していないひとに論理的に説明する素晴らしいお手本。
— A.I – Transition (@autumnyes) 2013年2月19日
『パイドン』(プラトン、岩波文庫)読了。この本のテーマは「魂について」。魂は肉体の牢獄に入れられているだけで、例え肉体が滅びようとも魂は不死なんだ!と言われても…。しかもソクラテスは死を喜ばしく語っているのだが、だったらなぜもっと早く死のうとしなかったのか?
— Ura-Hoshiya (@Moshiya314) 2012年6月15日
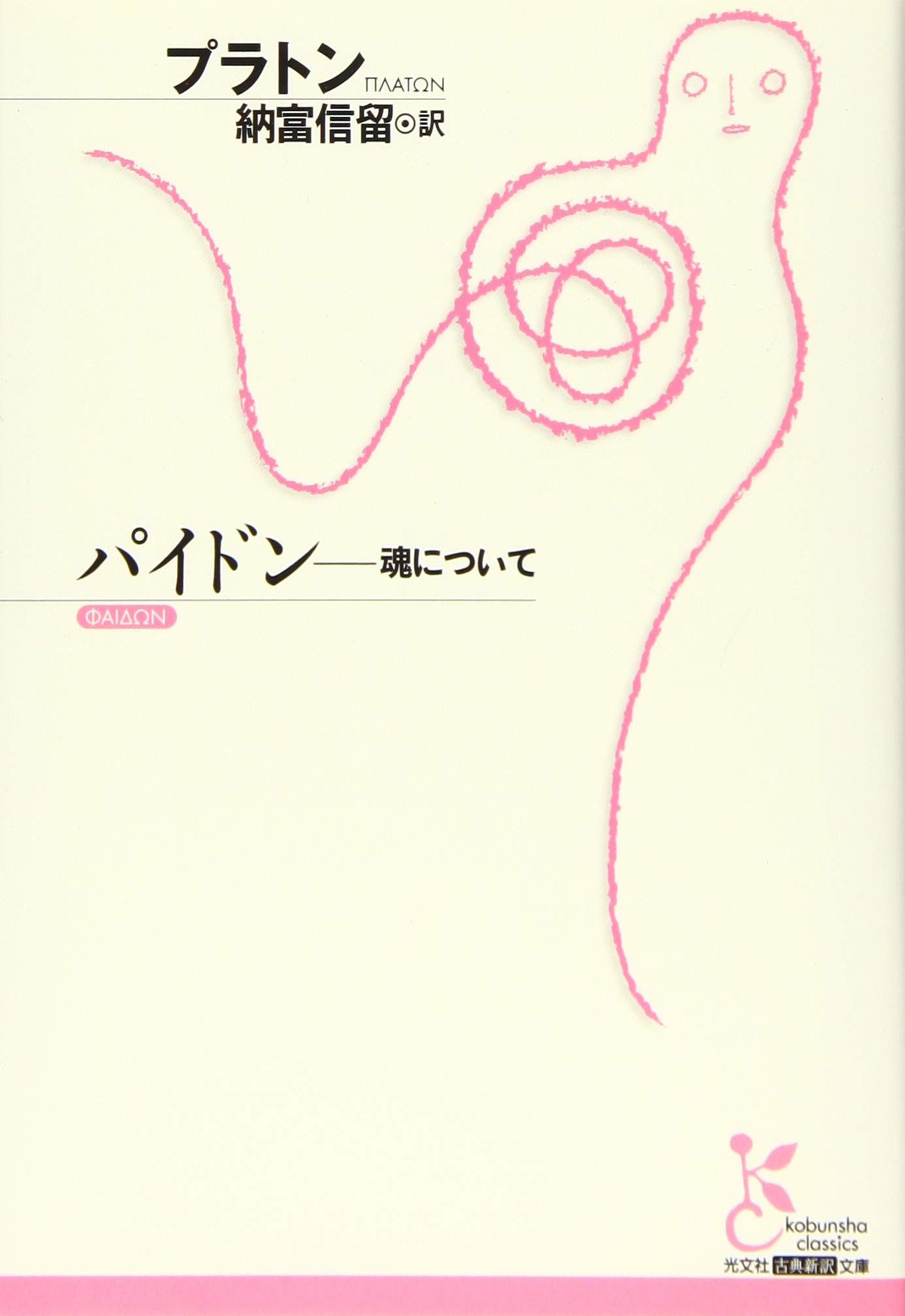




コメント