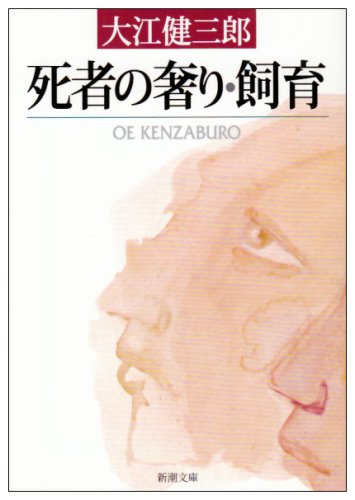大江健三郎が亡くなった
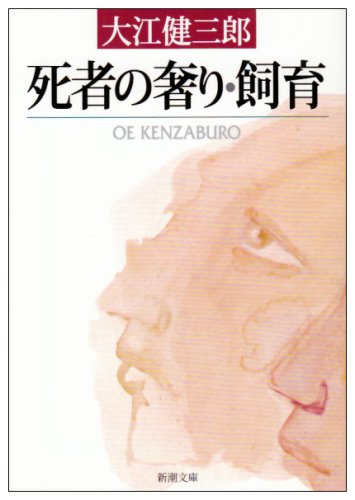 小説
小説
2023.03.13
[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
大江健三郎が亡くなった。
朝から雨の降る肌寒い日だった。コロナ禍の象徴ともなっているマスクの着用が今日から個人の判断に委ねられるという。早速マスコミ各社は朝の通勤ラッシュの様子を報道していたが、記事の写真を見る限りではマスクをしていない人はせいぜい十人に一人か二人といった程度だった。
金曜日に破綻した米シリコンバレー銀行の報道のせいかはたまた円高に振れたせいか、週明けの日経平均株価は311円安の27832円で引けた。無論売られたのは銀行株である。このところ日銀のYCC修正期待もあって買われていただけにその反動下げも大きかった。金曜日にはMSQ、そして黒田総裁下での最後の日銀会合の結果発表、米雇用統計の発表、米銀行の破綻が重なり、一度上抜けしたかのように見えた日経平均株価は再度下に向かい始めた。いわゆる”騙し”だったのだ。
僕が大江健三郎を読み始めたのは高校生の時だったはずだが詳細は覚えていない。初めて読んだ本は『死者の奢り・飼育』か『叫び声』だったはずだがそれすらも覚えていない。確実に覚えていることが二つあり、一つは大江健三郎の著作を初期から順番に読んでいったこと、もう一つは『万延元年のフットボール』が刊行されている講談社文芸文庫の値段が高く不満を覚えたことだ。
平成生まれの僕は大江を同時代の作家として読んでいったわけではなかった。阿部和重、伊坂幸太郎、中村文則。そうした作家たちに影響を与えたレジェンド、大家、ノーベル賞作家。そうした存在として読んでいった。だから伊坂幸太郎がインタビューで『叫び声』を褒めれば買い求めたし、『夜の国のクーパー』のあとがきに『同時代ゲーム』の名前が出れば手に取ったりもした。
大江の小説は難しかった。前述の『同時代ゲーム』もそうだし、『みずから我が涙をぬぐいたまう日』などはとりわけ難解で繰り返し読んでも内容を上手く理解することができなかった。その意味で僕は彼にとって優れた読者ではなかったかもしれない。僕が大江の小説で好きなのは彼が二十代や三十代の初めに書いた小説で、特に『叫び声』からは大きな影響を受けた。
僕と同じ世代、あるいは僕よりも若い人たちにとって石原慎太郎が小説家ではなく政治家であるのと同じように、大江健三郎を小説家というよりも政治活動家として認識している人もいるかもしれない。その勘違いから大江の小説に手を伸ばさないとしたら残念なことだ。僕は大江の理想主義みたいなところは嫌いだが、彼の小説は大好きだからである。どこかで中上健次も同じようなことを書いていたか言っていたはずだが、ソースが思い出せず紹介できないのが心苦しい。
タイトルとURLをコピーしました
[
'amazon' => ['label' => 'Amazon', 'color' => '#232f3e', 'base_url' => 'https://www.amazon.co.jp/s?k='],
'rakuten' => ['label' => '楽天市場', 'color' => '#bf0000', 'base_url' => 'https://search.rakuten.co.jp/search/mall/'],
'yahoo' => ['label' => 'Yahoo!', 'color' => '#ff0033', 'base_url' => 'https://shopping.yahoo.co.jp/search?p='],
'seven' => ['label' => 'セブンネット', 'color' => '#18943c', 'base_url' => 'https://7net.omni7.jp/search/?keyword='],
],
'ebook' => [
'kindle' => ['label' => 'Kindle', 'color' => '#ff9900', 'base_url' => 'https://www.amazon.co.jp/s?k='],
'kobo' => ['label' => '楽天Kobo', 'color' => '#cc0066', 'base_url' => 'https://search.rakuten.co.jp/search/mall/'],
'bookwalker' => ['label' => 'BookWalker', 'color' => '#0054a6', 'base_url' => 'https://bookwalker.jp/search/?word='],
'renta' => ['label' => 'Renta!', 'color' => '#e8bd16', 'base_url' => 'https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/search?word='],
'booklive' => ['label' => 'BookLive', 'color' => '#ff6600', 'base_url' => 'https://booklive.jp/search/keyword?keyword='],
'ebookjapan' => ['label' => 'eBookJapan', 'color' => '#e60012', 'base_url' => 'https://ebookjapan.yahoo.co.jp/search/?keyword='],
'cmoa' => ['label' => 'コミックシーモア', 'color' => '#ff911b', 'base_url' => 'https://www.cmoa.jp/search/result/?word='],
]
];
}
// --- 2. 管理画面の設定ページ作成 ---
add_action( 'admin_menu', 'mal_add_admin_menu' );
function mal_add_admin_menu() {
add_options_page( 'アフィリエイトID設定', 'アフィリエイトID設定', 'manage_options', 'mal_settings', 'mal_settings_page' );
}
function mal_settings_page() {
?>
に出力する機能 ---
add_action( 'wp_head', 'mal_output_linkswitch_tag', 1 );
function mal_output_linkswitch_tag() {
$tag = get_option('mal_linkswitch_tag');
if ( ! empty( $tag ) ) {
echo "\n\n";
echo $tag; // ここで設定画面のタグが出力されます
echo "\n\n";
}
}
// --- 4. ショートコード [shop_links id="商品ID"] ---
add_action( 'wp_head', 'mal_custom_css' ); // CSSの出力
function mal_custom_css() {
?>
'' ), $atts );
if ( empty( $atts['id'] ) ) return '';
$item_id = $atts['id'];
$services = mal_get_services();
$amz_id = get_option('mal_id_amazon');
$rak_id = get_option('mal_id_rakuten');
$output = '
';
foreach ( $services as $group_key => $group_data ) {
$label = ($group_key === 'physical') ? '【紙の本・総合通販】' : '【電子書籍】';
$output .= '
'.$label.'
';
foreach ( $group_data as $key => $data ) {
$url = $data['base_url'] . urlencode($item_id);
// Amazon/楽天だけは個別IDを付与(LinkSwitch対象外のため)
if (($key === 'amazon' || $key === 'kindle') && $amz_id) $url .= "&tag=" . $amz_id;
if (($key === 'rakuten' || $key === 'kobo') && $rak_id) $url = "https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/{$rak_id}/?pc=" . urlencode($url);
$output .= sprintf(
'
%s',
esc_url($url), $data['color'], $data['label']
);
}
$output .= '
';
}
$output .= '
';
return $output;
}