[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
ロボット工学三原則が初登場する近未来SF短篇集。創作の世界だけではなく、実際のロボット開発にも大きな影響を与えた。
われはロボット(アイザック・アシモフ)の作品情報
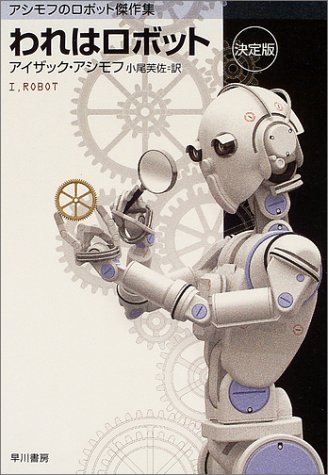
- タイトル
- われはロボット
- 著者
- アイザック・アシモフ
- 形式
- 小説
- ジャンル
- SF
ミステリー - 執筆国
- アメリカ
- 版元
- ダブルデイ社
- 執筆年
- 1940年―50年
- 初出
- 書き下ろし、1950年
- 刊行情報
- ハヤカワ文庫〔決定版〕2004年8月
- 翻訳者
- 小尾芙佐
われはロボット(アイザック・アシモフ)のあらすじ(ネタバレなし)
ロボットは人間に危害を加えてはならない。人間の命令に服従しなければならない…これらロボット工学三原則には、すべてのロボットがかならず従うはずだった。この三原則の第一条を改変した事件にロボット心理学者キャルヴィンが挑む「迷子のロボット」をはじめ、少女グローリアの最愛の友である子守り用ロボットのロビイ、ひとの心を読むロボットのハービイなど、ロボット工学三原則を創案した巨匠が描くロボット開発史。
映画版関連動画
実写映画『アイ,ロボット』2004年7月16日
作者
アイザック・アシモフ Isaac Asimov(1920年1月2日 – 1992年4月6日)
アメリカの作家、生化学者。SF、一般向け科学解説書、推理小説によってよく知られている。アシモフは、アーサー・C・クラーク、ロバート・A・ハインラインと合わせて三大SF作家 (The Big Three) と呼ばれる。SFの分野でヒューゴー賞を7回、ネビュラ賞を2回、ローカス賞を4回受賞している。
われはロボット(アイザック・アシモフ)の刊行情報
- 伊藤哲訳『わたしはロボット』 創元SF文庫、1976年
- 小尾芙佐訳『くるったロボット』岩崎書店、1976年
- 小尾芙佐訳『われはロボット』ハヤカワ文庫、1983年
- 小田麻紀訳『アイ・ロボット』角川文庫、2004年
- おすすめ小尾芙佐訳『われはロボット〔決定版〕アシモフのロボット傑作集』ハヤカワ文庫、2004年
われはロボット(アイザック・アシモフ)の登場人物
スーザン・キャルヴィン
女性。USロボット社の主任ロボ心理学者。本作は82歳で亡くなったキャルヴィン博士の回顧録という形式を取っている。
ドノヴァン
USロボット社の新型ロボット実地テスト担当員。
パウエル
USロボット社の新型ロボット実地テスト担当員。
われはロボット(アイザック・アシモフ)の解説・感想・評価
#われはロボット(#アイザック・アシモフ)#読了
— 右手@文学&副業ブロガー (@migite1924) 2019年9月3日
有名なロボット工学三原則が初登場するSF作品。
ロボットによるトラブルが話の中心。ロボットが自己存在について考えたり、人の心が読めたりと草創期の作品でここまで切り込んでいたんだなと。人間らしさについて考えました#読書好きな人と繋がりたい pic.twitter.com/OljC3VwS8s
ロボット工学三原則が初登場する近未来SF
アシモフの初期のロボットSF短編を収録した短篇集となる。本作の巻頭において初めてロボット工学三原則が示された。
第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
小尾芙佐訳『われはロボット〔決定版〕アシモフのロボット傑作集』ハヤカワ文庫六刷
第二条 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条 ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
—『ロボット工学ハンドブック』、第五十六版、西暦二〇五八年
舞台は現代より少し技術の発達した近未来。すでに世界に国家や戦争はなく、ニューヨークを首都に地球には三十三億の人間が暮らしている。
本作はロボット心理学者のスーザン・カルヴィンが記者のインタビューに答えるという回顧録として描かれる。ロボットが人間と共に活動する中で、様々なトラブルが発生し、その原因を探るというストーリーだ。そのためSF小説であるとともに、ミステリー小説でもある。そして作中では「ロボット工学三原則」が明示される。
ロボットと人間らしさ
ロボット工学三原則第一条では「ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。」とする。
すなわちここでは、ロボットと人間が違うことが示されるわけだが、本作では世界はいくつかの地区に分かれ(ユーロ、北米圏、東アジアなど)すでに国家や戦争はなくなっており、雇用問題や食糧問題も過去のものになっている。
そんな世界で人間とロボットはどのように区別されるのか?つまり、ロボットに対する人間らしさというものが本作で問題提起される。
私たちが住む現実の社会でも今後ロボットはどんどん普及していくことになるだろう。いまの子どもたちが、生まれたときからコンピューターやスマートフォンに接しているように、生まれたときからロボットに接する世代も出てくるだろう。
そのときにロボットにない“人間らしさ”とは何なのか。そのことを考える必要性・必然性を本作は訴えている。
合わせて読みたい本
ロボットの時代 〔決定版〕 アシモフのロボット傑作集
月世界開発用に調整されたロボットが地球上で行方不明になって起こったとんでもない大騒動を描く「AL76号失踪す」、地球から派遣されたロボットと木星人との奇妙な遭遇「思わざる勝利」、美男子の召使いロボットのトニイと女主人クレアのただならぬ関係を描く「お気に召すことうけあい」など、様々なロボットたちの様子を描きます。
『われはロボット』の姉妹編となる短篇集です。
われはロボット(アイザック・アシモフ)の評判・口コミ・レビュー
われはロボット(旧版)読了。ロボット工学三原則に基づくロボットのエラー的行動をロボット心理学のスーザン・ギャルヴィン博士が推理していく、短編で構成されているロボット開発史を博士の回想録という形で1つの物語にまとめられている極上のSF pic.twitter.com/RNfNYNNiQh
— んぱ(npa)@生食パンウンメー (@npa_featherstar) 2016年5月19日
アイザック・アシモフ『われはロボット』読了。SF作品として、ロボットや宇宙といった題材の面白さは言うまでもないが、それらに通底する論理に徹底して誰もが対面できる、あるいは対面させられる物語作りがなされているのが、本作の素晴らしさではないかと思う。ミステリ的というか、人間的な小説。
— 逸見文 (@ItsumiAya) 2014年6月28日
われはロボット
— 五月湧🎄RAFE〈改〉 (@May_Justyna) 2019年12月22日
アイザック・アシモフ 読了
いろんなロボットが問題を起こす、短編傑作集。ロボット工学の三原則という、人間とロボットとの決まり事の捉え方で解決していく。その爽快感がたまらない。次の「ロボットの時代」を早く読みたいです!#日本SF読書クラブ
45 アシモフ 『われはロボット』
— とおり人@読書 (@itotokami) 2019年12月19日
「ロボット工学三原則」を生んだ、
SF史において外せない作品。
ロボット工学三原則にまつわるミステリーとしての面白さは勿論、人間という存在をめぐる深い哲学性も備えたエピソードが語られる。
なおかつ読みやすいというのが凄い。#人生のベスト100冊 #読了 pic.twitter.com/jE0uzy4mBc
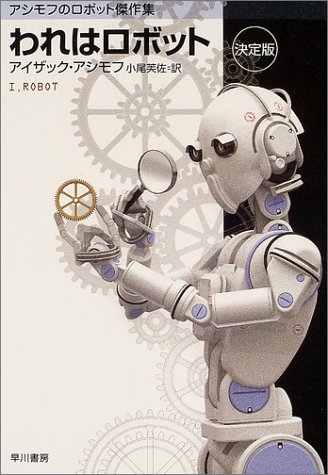




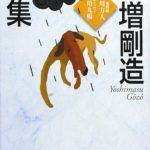
コメント