[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
宿神=シャグジ。国家誕生とともに埋葬され、忘れられた精霊である。
精霊の王(中沢新一)の作品情報
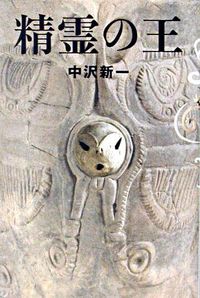
- タイトル
- 精霊の王
- 著者
- 中沢新一
- 形式
- 学術書
- ジャンル
- 民俗学
文化人類学
考古学
歴史学
芸能学 - 執筆国
- 日本
- 版元
- 講談社
- 初出
- 群像、2002年1月号~2003年3月号まで計12回
- 刊行情報
- 講談社、2003年
精霊の王(中沢新一)の概要・あらすじ
“魂の原日本”を求めて縄文へと遡る思考の旅。宿神の秘密を明かす奇跡の書、金春禅竹『明宿集』現代語訳も収録。
目次
- 第1章 謎の宿神
- 第2章 奇跡の書
- 第3章 堂々たる胎児
- 第4章 ユーラシア的精霊
- 第5章 緑したたる金春禅竹
- 第6章 後戸に立つ食人王
- 第7章 『明宿集』の深淵
- 第8章 埋葬された宿神
- 第9章 宿神のトポロジー
- 第10章 多神教的テクノロジー
- 第11章 環太平洋的仮説
作者
中沢新一(1950 – )
思想家、宗教史学者。明治大学特任教授/野生の科学研究所所長、多摩美術大学美術学部芸術学科客員教授。クロード・レヴィ=ストロース、フィリップ・デスコーラ、ジャック・ラカン、ジル・ドゥルーズ等の影響を受けた現代人類学と、南方熊楠、折口信夫、田邊元、網野善彦等による日本列島の民俗学・思想・歴史研究、さらに自身の長期的な修行体験に基づくチベット仏教の思想研究などを総合した独自の学問「対称性人類学」を提唱する。
精霊の王(中沢新一)の刊行情報
『精霊の王』講談社、2003年11月
『精霊の王』講談社学術文庫、2018年3月
精霊の王(中沢新一)の感想・解説・評価
国家的神話以前の神・ミシャグチを巡る冒険
柳田国男『石神問答』で言及された国家的神話以前の神・ミシャグチを巡り、様々な思考が展開される。このミシャグチ、別名をシャグジ、ミシャグジ、シュクジンなどという神は、石の神だ。日本の神の体系には含まれたことがなく、忘れかけられていた。日本列島に国家や神社が成立する前の時代にいたるところに分布した古代神だという。
ミシャグチと言われても多くの人には馴染みのないものだと思うが、別名のひとつ・シャグジから石神井(しゃくじい)という地名を連想することができればその存在は一気に身近になる。石神という単語が含まれていることからも、石神井という地名がミシャグチの異名から来たことがわかる。
「それは神というよりはむしろ精霊と呼んだほうがよいような、とてつもない古さを秘めている。かつてその精霊はこの列島上のいたるところに生息し、場所ごとに少しずつちがった呼び名で呼ばれていた。シャグジ、ミシャグジ、シャクジン、シュクジン、シュクノカミ、シクジノカミなどというのが、この精霊の名称の一部であるが、柳田国男はそうした呼称すべてに、「サ音+ク音」の結合をみいだすことができることを発見していた。この形をした音の結合は、きわめて古い日本語でものごとや世界の「境界」を意味するものだった。この精霊は、古代の人々が空間の構造や事物の存在を認識するうえで、とても大きな働きをしていたことが、これによってあきらかにされた。
『精霊の王』中沢新一、講談社
中沢は、先行する民俗学・文化人類学・考古学・歴史学・芸能学など複数の学問を越境的に踏まえつつ、ヨーロッパの研究成果をも吸収し、未完成のままとなった柳田国男の『石神問答』にひとつの発展形態をもたらすという課題に取り組んでいる。
中沢新一独自の知の旅
柳田国男『石神問答』で言及された国家的神話以前の神・ミシャグチについて触れるところから本書は幕を開ける。しかし内容はそれだけにとどまらない。金春禅竹の『明宿集』などから、読者は中沢新一独自の知の旅に出発することになる。
柳田國男の石神問答、折口信夫の翁論、諏訪のミシャグチ神、ユーラシア全体に広がる精霊…と題材を変えながら旅は進行。その間に読者はプラトンから吉本隆明、ディケンズから中原中也と作者の頭の中を覗き込んでいくことになる。
精霊の王(中沢新一)の評判・口コミ・レビュー
#中沢新一「#精霊の王」#読了
— 右手@文学&漫画ブロガー (@migite1924) 2019年9月15日
柳田国男の「石神問答」の国家的神話以前の神・ミシャグチから出発し、民俗学、文化人類学、芸能学など様々な学問を越境的に横断しながら論じた本。
人類史全体を描こうとした壮大な一冊なだけに一回ではなかなか読み取れず。知の旅を楽しめる背景知識がもっと必要でした pic.twitter.com/dxNptkCvFy


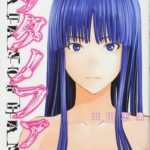

コメント