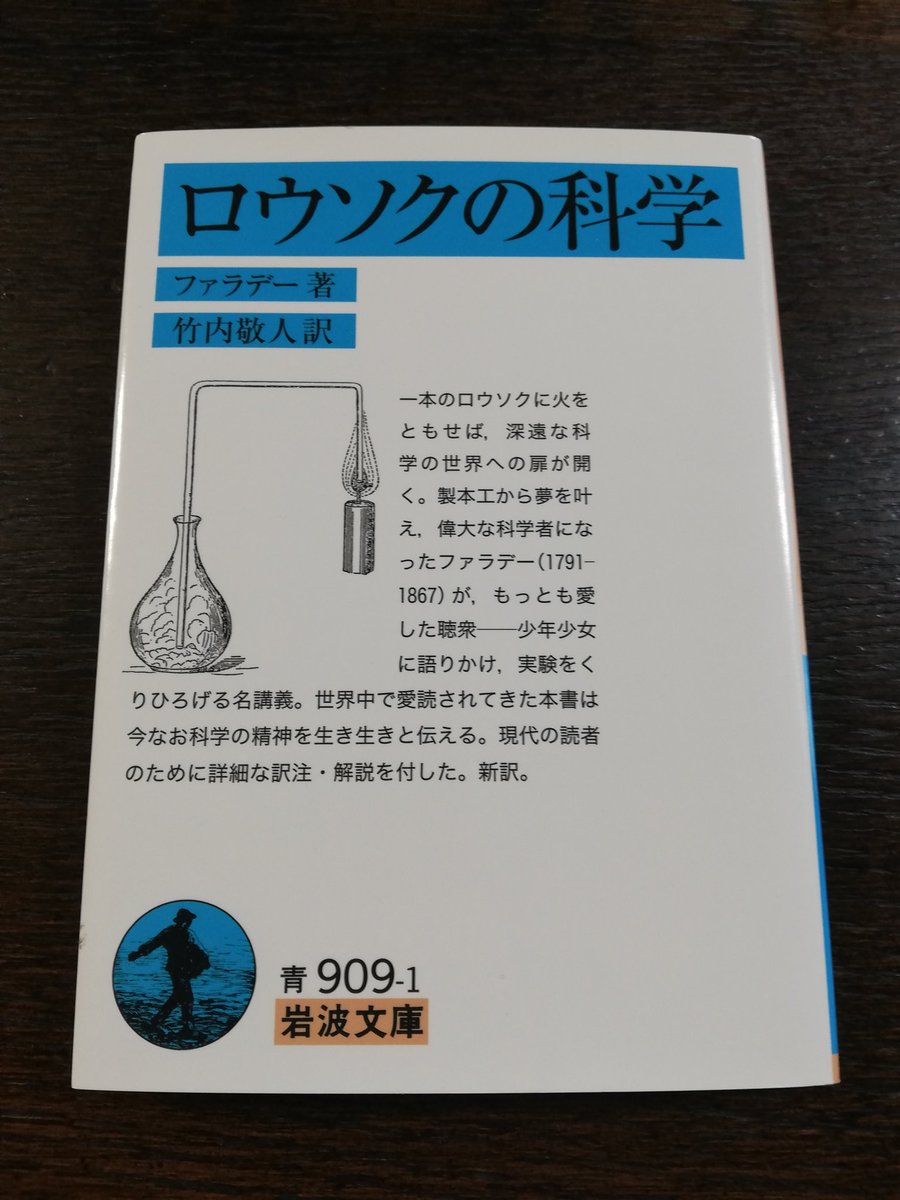[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。
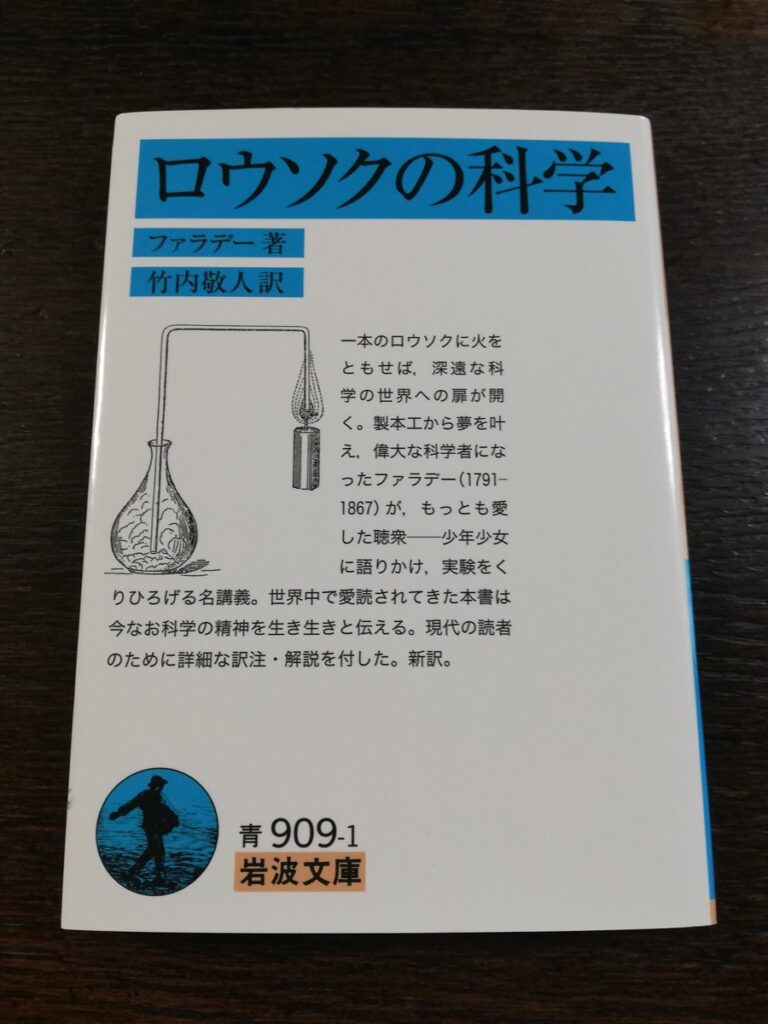
今日は「可能性」の話です。
というのも歳とるにつれ「もし○○だったら、こんな未来もあったのかな」とか無意味な妄想に耽るじゃないですか。
もし○○(スポーツ)やってたら、プロになれてたんじゃないかなとか。まったくやったこともないのに、実はそっち方面の才能あったんじゃないかなとか。
もちろんそんなことなくて、(超)一流と素人の差はコミットした時間という研究結果もあるくらいです。つまり「才能があると言われていた人ほど、時間をかけて練習・研究していた」という話ですね。
ノーベル化学賞で話題の「ロウソクの科学」を読んだ
そんなことを考えたのも、ノーベル化学賞で話題の「ロウソクの科学」を読んだからです。受賞者の吉野彰さんが会見でタイトルを出していたんですね。
#ノーベル化学賞 で話題の #ロウソクの科学 を読んでるんですが、(積読本の中にあった)「僕がノーベル化学賞受賞者になる可能性はなかったな」ということだけはわかりました😇
— 右手@文学&漫画ブロガー (@migite1924) 2019年10月11日
根っからの文系気質なのかな pic.twitter.com/relgAczyVF
買ったけど読むことなく放っておいた、いわゆる「積読本」の中にありました。買った記憶はないんですけど、たぶん「岩波文庫だから読んでみるか」くらいの感覚だと思います。
それで、読んでみたんですけど、とくに興味がわかなかったですね。「ロウソクの科学」は岩波文庫、角川文庫、角川つばさ文庫、かつては旺文社文庫でも刊行されている名著なんですけどね…
「ロウソクはなぜ燃えるのか?」という疑問から、化学や科学について語った公演の記録をまとめた本になります。かなりわかりやすく語られており、小学生くらいの年代の子でも充分読めると思います。角川つばさ文庫ものなら間違いないですね。
なんですが…なんていうか、本文や図のイメージが頭に留まらずに、頭の中を通り過ぎていくような感じがしました。
たぶんですが、そもそも酸素とか二酸化炭素とか燃焼とか液体とか固体とかいうものに興味がないんでしょうね。
小学生の時に、読書の時間が設けられていたんですが、友たちが恐竜の図鑑やウォーリー探せを読んでいる傍ら、偉人の伝記やズッコケ三人組を読んでいたことを思い出しました。なぜかノーベルやキュリー夫人が好きでしたね。(ノーベルはダイナマイトを作った人なんですよ!それまで爆薬は液体で管理が難しく事故が頻発していたんですが、固体になって格段に扱いやすくなったんです)
僕は子どものときからそんな感じだったので、「もし小学生や中学生の時にロウソクの科学を読んでいたとしても変わらなかっただろうな…」と思いました。
ヒカルの碁がきっかけで囲碁を始めたりはしたんですけどね。根っからの文系気質というか、本の虫なのかもしれません。子どものころに本を読んでいると「偉いね」と褒められたもんですが、大人になるとむしろ邪険に扱われがちです。
おわり。